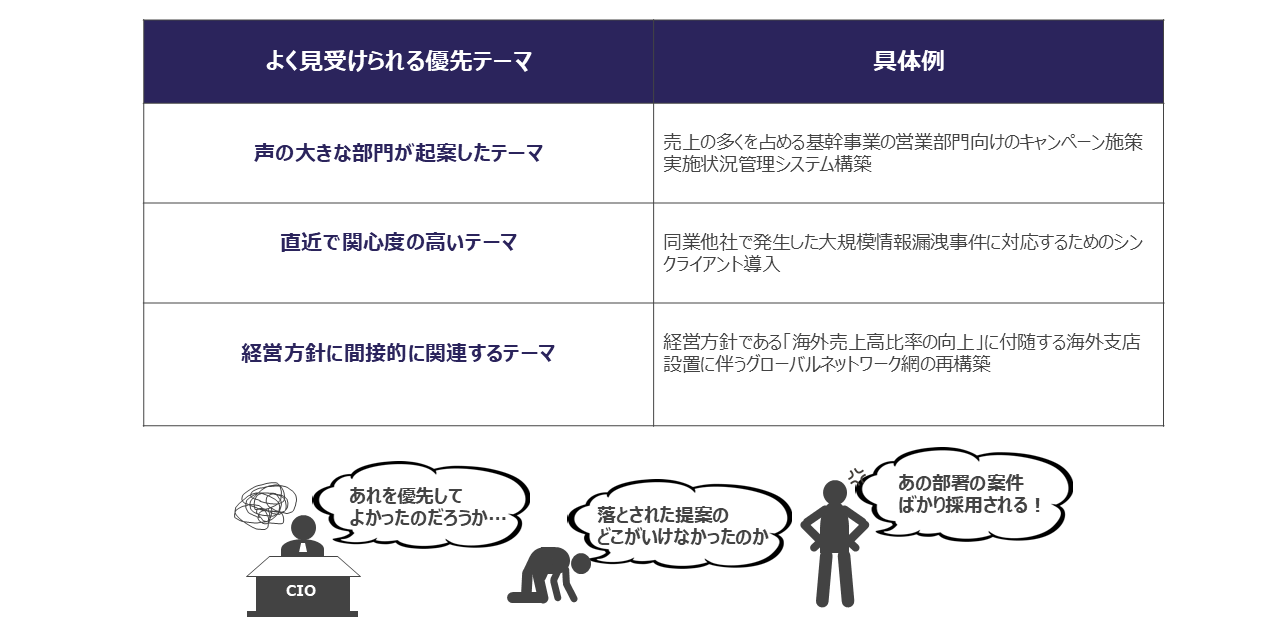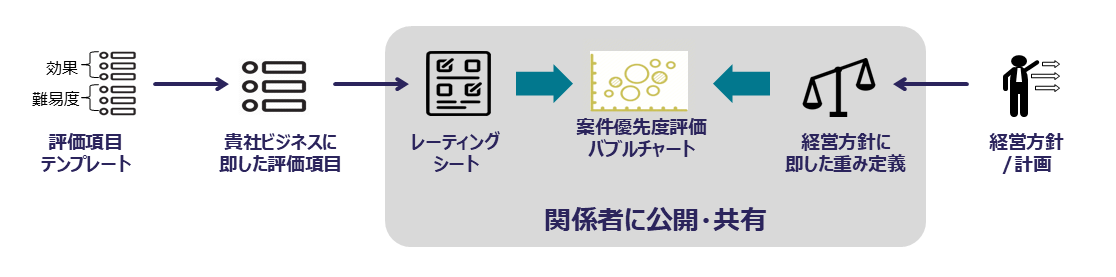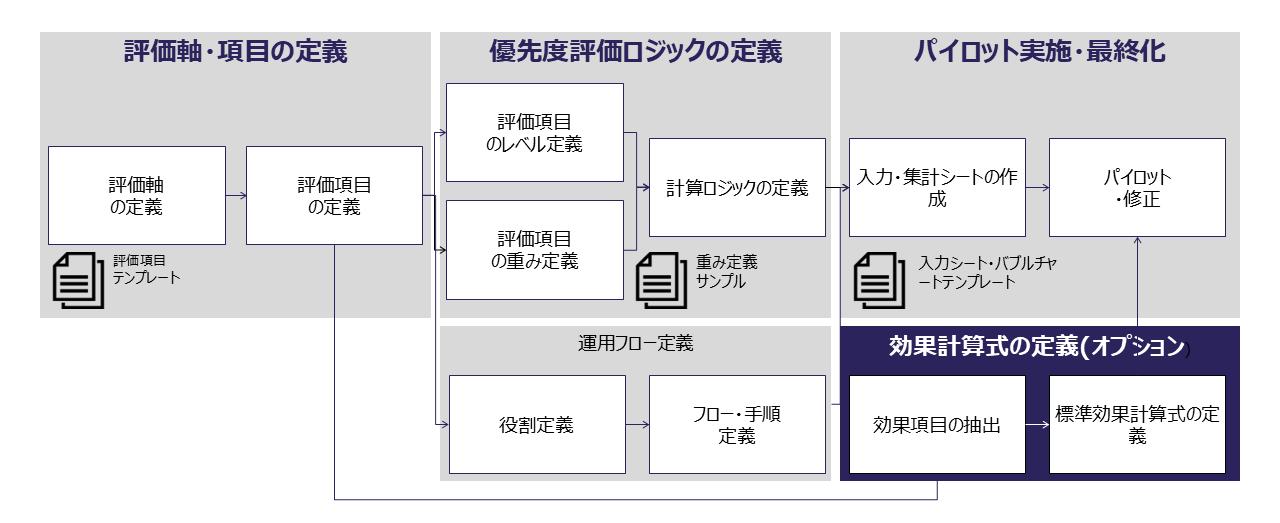サプライヤーマネジメントの進化
~「サプライヤーマネジメント」から「戦略的サプライヤーマネジメント」へ、そして「バーチカルチェーンマネジメント」へ~
昨今、供給不足やサプライチェーン分断、地政学リスクの顕在化などにより企業を取り巻く環境が大きく変わる中、企業はサプライチェーン全体でQCD+αの適正化を実現する取り組み「戦略的サプライヤーマネジメント」に取り組んでいく必要があります。 本ホワイトペーパーでは、従来のサプライヤーマネジメントと戦略的サプライヤーマネジメントの違いや実現事例を取り上げます。 また、今後、調達購買部門主導で企業の競争力強化を実現する有効なアプローチとして、川上から川下までを含むバーチカル(垂直)でバリューチェーンを最適化する「バーチカルチェーンマネジメント」の概念や取り組みについても紹介します。