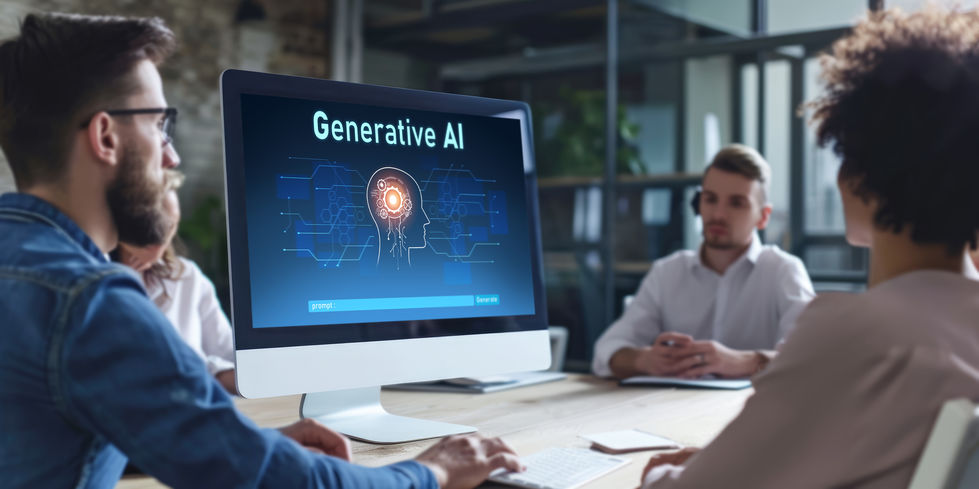
目次
サマリー
- 生成AIは日本企業において急速に導入が進んでいるものの、PoC止まりや制度設計の未整備などにより、多くの企業で業務定着には至っていない。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)や情報サービス産業協会(JISA)の調査でも、効果測定の未実施や属人化が大きな課題として挙げられている
- こうした課題を克服し、生成AIの投資対効果(ROI)を最大化するには、活用状況を可視化し、部門・個人別の支援や育成方針を戦略的に設計・実行できる必要がある。そのための有効な手段が、「成熟度マトリクス」によるアセスメントである
- このマトリクスは汎用的な評価軸として、単なる技術の活用有無だけでなく、組織的な浸透度や価値創出の度合いまでを測定可能にし、定着度を基に施策優先度やトレーニング設計、ROI判断の基盤にできる。また、人的資本経営の観点からも、スキル定義と成熟度レベルに基づいた育成設計や資源配分は不可欠であり、既存の人材評価制度との整合も求められる
- 加えてスキルの偏在や属人化、スキル定義の陳腐化といった課題に対しては、継続的なアセスメントとマトリクスの見直しにより対応する必要がある。生成AIの本質的な価値を引き出すにはPoCの数ではなく、生成AIがいかに業務に根づいているかを評価することが今後の競争力の差を決定づける
1. 生成AIの「定着」を測る:組織成熟度マトリクスによるアセスメントとその経営的意義
日本企業における生成AI導入の現状
生成AI技術は、2023年以降、国内外の産業に急速に浸透している。日本国内においても、大手企業を中心に「全社導入」や「PoCの拡張」が進んでいるが、その多くが定着フェーズに至っていないのが実態である。
実際、IPAが公表した『DX動向2025』によれば、国内企業における生成AIの業務利用は「個人や部署で試験利用している」に留まるケースが過半数を占めており、「部署の業務プロセスに組み込まれている」段階まで活用が進んでいる企業は少ない。[1] JUASの「企業IT動向調査2025」によると、生成AI導入企業の約7割が何らかの効果を実感している一方で、約6割が効果測定を行っておらず、成果評価が十分に行われていない。さらに、日常業務で生成AIを活用している従業員は8.4%にとどまり、活用が一部社員に依存している実態が明らかとなっている。[2]
導入後の共通課題と“定着”の必要性
こうした状況において多くの企業が抱える共通課題は、「生成AIを導入したものの、実際に現場で活用されているのか」「どの部門や業務で、どのような成果が出ているのか」が把握できず、施策や投資の方向性が定まらない点にある。つまり、“導入したが使われていない(もしくは使われているかわからない)”という状態が、生成AIの真の価値を毀損している。
では、なぜ生成AIの定着がこれほど重要なのか。
2025年以降、生成AIの業務活用度合いは企業の競争力を左右する重要因子となる。海外では、生成AIを活用した業務自動化や顧客体験の高度化により、ROIを明確に可視化する事例が増えており、活用度をKPIとして管理する動きが加速している。こうした潮流を踏まえ、日本国内においても、生成AIを単なる効率化ツールにとどめず競争優位につなげるための論点整理が進みつつある。たとえば、経済産業省『生成AI時代のDX推進に必要な人材・スキルの考え方2024』では、業務効率化・生産性向上にとどまらず、製品・サービスやビジネスモデル、組織文化等の変革を通じた競争上の優位性の確立に生成AIを活用することが期待されるとされ、あわせて経営層の姿勢・関与や推進人材とスキル等が乗り越えるべきハードルとして整理されている。[3]
一方、日本企業ではアクセス権限の付与やツール選定で議論が止まりがちであり、「業務レベルで活用されているか」「再現性あるユースケースが共有されているか」といった定着視点が十分に設計されていない。その結果、生成AIが一部社員の「便利ツール」にとどまり、組織としての生産性向上にはつながっていない構造がある。
さらに生成AIは日進月歩で進化しており、モデルや機能は数ヶ月単位で大きく更新される。したがって、“現時点でどの機能を使いこなせているか”といった静的なスキル評価はすぐに陳腐化し、個人や組織の本質的な成長度合いを測る指標としては限界がある。むしろ、変化の激しい技術に対して継続的にどのように向き合い、学習し、業務に取り入れているかを捉える「成熟度」こそが、生成AI時代における能力開発を測定する重要な視点となる。
そこで企業に求められるのは、生成AI活用の実態(どこまで業務に組み込まれているか、どの層・部門で滞留が起きているか)を“共通のものさし”で捉え、育成・支援・投資の意思決定につなげられる状態を整えることである。
「生成AI活用の成熟度」を段階的に可視化することは、単なる現状把握にとどまらず、以下のような複数の目的で活用できる:
- 定着度合いを定量・定性の両面で評価し、施策や支援の優先度を明確化する
- レベル別に必要なトレーニング・育成方針を設計する基盤とする
- 経営としての投資判断やROI評価の指標とする
このように、成熟度マトリクスは生成AIの導入・利活用を戦略的にマネジメントするための重要な起点となる。
2. 人材育成指針との整合:スキルマトリクスと成熟度の可視化
生成AIを業務に定着させる上で、技術導入と並んで重要となるのが「人材」の評価軸である。多くの企業で導入が進むIPAの「ITスキル標準(ITSS)」や、経済産業省とIPAが定義した「DXリテラシー標準」が示すように、業務を担う人材のスキル状態を段階的に可視化することは、投資効果の定量評価や人材開発の方針策定に不可欠である。
生成AIに関しても同様に、業務活用スキルのレベルを定義し、それぞれの状態に応じた育成目標や支援施策と結びつける設計が求められる。レベル設計は、自社の人材戦略や活用状況に応じて柔軟に設計すべきである。たとえばカテゴリー別に成熟度マトリクスを設けることで、形式的な利用率ではなく、実質的な業務浸透度やスキルの再現性を評価することが可能となる。
特に注意が必要なのは、これらの定義が既存の社内フレームワーク(例:人材類型、人事制度、DX推進体制)と整合していない場合、現場での混乱や納得感の欠如につながる点である。したがって、成熟度マトリクスは「外部フレームワークの単純転用」ではなく、自社の人材開発体系や組織文化に適合させた設計が求められる。
3. 成熟度マトリクスとアセスメント設計:活用の実態を捉えるには
実際には、以下のような成熟度マトリクスを基に、簡易的な手段としてアンケート形式のアセスメントを用いることが多い。必ずしもアンケートに限る必要はなく、業務ログの分析や1on1ヒアリングなど、組織の状況に応じた柔軟な手法で定着度を評価することが可能だ。
本稿で提示するマトリクスは、特定の業種や企業に依存しない汎用的な視点で設計されたものである。生成AIは日進月歩で進化し、機能やツールの習熟度といった静的なスキル評価はすぐに陳腐化する。そのため、個人が“今の機能を使いこなせるか”だけを測定しても、実質的な成長度合いや組織としての価値創出力を適切に捉えることは難しい。
そこで本マトリクスでは、個人のスキル基盤(Capability)に加え、属人化を防ぎ組織として学習を蓄積するための協働・共有の度合い(Collaboration)、さらに業務成果や顧客価値への貢献(Contribution)という3つの観点を評価軸として設定している。この3Cを組み合わせることで、単なる利用状況の把握にとどまらず、変化の激しい生成AIに対して継続的にどう向き合い、どれだけ組織として価値創出につなげているかを多面的・動的に評価できるようにしている。
※本マトリクスは一例であり、目的や業種特性に応じてカスタマイズが必要である。
評価の観点は「できるか/できないか」ではなく、活用方法が他者にも展開できる形で型化・標準化されているか、また、知見共有が行われているかといった定性的な要素が重視されるべきである。形式的な利用回数ではなく、業務貢献につながる活用の質を評価軸とすることで、投資対効果をより正確に捉えることが可能となる。
なお、誤解してはならないのは、成熟度とは「個々人のスキル」だけを意味するものではないという点である。生成AIの定着においては、チームメンバー間での協働や知見の共有、組織的成果の創出といった「組織としての成熟度」も不可欠である。したがって、マトリクス設計の段階で、個人・チーム・組織の各レベルにおける指標をバランスよく設けることが望ましい。
4. 実務で直面する課題と教訓
導入後の活用促進においていくつかの共通課題が繰り返し観察されている。その中でも特に頻発するのが、スキルの偏在による「成熟度の停滞」である。たとえば組織内にレベル3以上の活用者が存在していても、大多数のメンバーがレベル1〜2の状態では、現場全体のボトムアップが起こらず、生成AIの恩恵が局所的なものにとどまる。
また、生成AIに精通した一部のメンバーに依存し、組織全体としての学習や育成が進まないケースも多く見られた。その結果、PoCレベルでの導入は成功しても、活用が定着せず成果につながらない「部分最適」状態が発生するリスクが高い。局所的な活用が続く限り、投資効果は組織全体に広がりにくい。したがって、成熟度の分布を可視化し、停滞している層に合わせて打ち手を設計することが不可欠である。
さらに見落とされがちなのが、「スキル定義そのものの陳腐化」である。生成AIを取り巻く技術や活用方法は、半年単位で大きく進化する。そのため、最初に設計したマトリクスや評価軸も、定期的に見直し・更新する前提で運用する必要がある。従来のITスキルアセスメントに比べ動的なマネジメントが求められる点で、運用設計にも柔軟性が問われる。
5. 経営層への提言:定着度=ROI指標としての活用を
生成AIの「定着度」を測ることは、DX投資のROIを可視化するうえで極めて実効性の高い手段である。導入率や利用回数ではなく、「業務成果への寄与度」を測定指標とすることで、経営としての投資妥当性を明示できる。
成熟度マトリクスは、AI活用がどの業務にどれだけ深く浸透しているか、どの程度生産性や付加価値創出に寄与しているかを定量的に把握するための枠組みである。これは単なる技術導入の指標ではなく、次の資源配分を決める経営意思決定の土台となる。
そのためには、まず自社にとって「何ができていればレベル3か」「どのような行動が業務貢献とみなされるか」といった評価基準を明確に定義し、それを人材フレームワークと接続する必要がある。これにより、現場での納得感と活用意欲を両立した施策展開が可能になる。
生成AI活用の成功は、「PoCの数」ではなく、「どれだけ根づいたか」によって測られる時代に突入している。人・組織・業務に根差した評価軸をいかに早く構築できるかが、企業の将来的な競争力に決定的な差を生み出す。
6. おわりに
生成AI活用は“導入”ではなく“定着”によって成果が決まる。成熟度マトリクスは、活用状況を可視化してボトルネックを特定し、投資・育成・支援の優先順位を整えるための実務的な起点となる。重要なのは、一度評価して終わるのではなく、継続的に見直しながら組織として学習を蓄積していくことである。
[1] IPA 独立行政法人情報処理推進機構(2025), “DX動向2025”,
https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/dx-trend/tbl5kb0000001mn2-att/dx-trend-2025.pdf(参照2025年12月18日)
[2] JUAS 一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会(2025), “生成 AI の利用状況(「企業 IT 動向調査 2025」より)の速報値を発表”, https://juas.or.jp/cms/media/2025/02/it25_2.pdf(参照2025年12月18日)
[3]経済産業省(2024), “生成AI時代のDX推進に必要な人材・スキルの考え方2024”,
https://www.meti.go.jp/press/2024/06/20240628006/20240628006-b.pdf(参照2025年12月18日)












