組織の未来をデザインする人的資本経営の力
Talent Management Review vol.3
近年、ESG経営や無形資産を重視する国際的な動きや国内の雇用関連制度改善の動きを受け、企業に人的資本経営の推進や人的資本に関する情報開示を求める動きが活発化しています。非常に良い傾向だと思われる一方で、懸念される事象も起きています。 本稿では、人的資本経営を組織の未来をデザインするための力とするべく、求められる姿勢や視点を紹介します。

昨今、チェンジマネジメントは一般的な概念となり、プロジェクトマネジメントでは既知の概念であり、リーダーシップ育成の一貫としては熟達するに相応しいコンピテンシーであるとも考えられています。効果的なチェンジマネジメントを行うことでプロジェクトを成功裏に完了させ期待した成果が実現されます。しかしながら改革プロジェクトの多くは、ソリューションを効果的に実行できず期待した成果を上げられないままとなっています。業務プロセスのグローバル化、基幹システムの導入や再構築など大規模な改革を成功させるためには組織レベルでの合意形成と、社員個々が自律的参画に基づく新しい変化(新プロセス・技術の変化による新たな内部関係・インターフェース・役割・求められるスキル)を十分に理解し適応することが必要不可欠となります。改革における理想と現実のギャップをPeopleの視点で分析し、チェンジマネジメント推進に関連するステークホルダの役割を明確化し、方向性と計画を示す共に社内関連部署及び社外取引先に対する業務変更点を洗い出し、ステークホルダーが抱える要因の特定と、特定された要因の対応策の策定、そして、ニーズに合わせたトレーニングや社内外へのコミュニケーション施策を策定・支援します。
POINT 1
BPRなどの変革の現場で挙がってきた声は下記のように分類され、それらのギャップが変革に対する抵抗要因となります。
POINT 2
変革活動が失敗する要因としては、以下のようなものが一般的には言われています。
■継続的ではなく一時の活動で終わった
■プロジェクト オーナーが頻繁に変わった
■プロジェクト オーナーの意欲や意志がそれほど強くなかった
■変化に対する現場の抵抗に効果的に対応できなかった
■コンセンサスの形成が足りなかった
■手段やツールだけに力を注いだ
■推進するための優秀な人材が足りなかった
■プロジェクトの推進過程管理/評価/補償体制が足りなかった
■根本的な変革はなく部分的な改善にとどまった
POINT 3
業務改革/IT改革の実行過程において、変化に対応していくために人の意識・知識を正しく浸透させることが重要です。 いかにすばらしい業務プロセス・システムを設計しても実践する人の意識を変えられなければ成果はありません。 「変革の意味」を浸透させていくためには、関係者ごとに意識レベルをプロジェクトの進度に応じて段階的に高めていくことが重要です。
POINT 4
プロジェクトを成功裏に遂行するために、啓蒙とコミュニケーション、トレーニング、組織/評価の変革というチェンジマネジメントの4大タスクを効率的に推進し、参画者の意識と知識の変革を行い、変化に対する不安感をなくし、新しい業務プロセスや情報インフラの環境に容易に適応できるように、永続的に支援することです。
POINT 5
①多数の成功事例をベースに、弊社はチェンジマネジメントの方法論が確立されており、クイック且つ品質よく立ち上げることが可能です。
②必ず10年以上のSAP導入経験および、業務コンサルティング経験が共に豊富なメンバーがコアに備えてチーム編成になっています。
③SAP関連業務機能だけではなく、関連ユーザーの全業務機能をトータル的に業務設計し、SAPを最大限に活用しながら、全体的にスムーズな運用ができる業務設計を主眼にしています。
④新規業務設計時、重要な変革ポイントを顕在化し、それらを中心に、業務設計、ルール定義および教育を徹底的に実施しています。
⑤導入手法に、通常のトレーニング、UATだけではなく、業務負荷確認および、運用の実現性も検証できる実業務シミュレーションも可能にしています。
業務側のチェンジマネジメントタスクとして、パッケージ基幹システム導入に関する業務的・技術的専門知識と経験を持ったメンバーが計画、準備および、実施の支援をさせていただく事で、プロジェクト成功に貢献できるものと考えております。 チェンジマネジメントのアプローチとして、マスタスケジュールを策定する段階で、チェンジマネジメントに関連するタスクをスケジュールに表します。
POINT 6
チェンジマネジメントにおけるフェーズ別タスクと主要作成資料は、概ね記載のとおりとなります。 ビジネス設計/実現化フェーズのトレーニング方針/計画策定のタスクでは、主要作成資料に記載されているもの全てを作成するわけではなく、必要に応じて作成となります。 例えば、ユーザー配付用マテリアル作成方針を策定した上で、業務マニュアルや操作マニュアルを作成するのか、もしくは、従来の保守運用資料(フォーマット)に準ずるであれば作成方針は不要となります。 また、プロジェクトによっては、システム化業務フローを流用加工し、業務マニュアルと操作マニュアルを兼ねて作られた例もあります。 改めてお伝えするまでもなく、プロジェクトの状況に応じて、必要なものを必要なタイミングで作成することになります。
Talent Management Review vol.3
近年、ESG経営や無形資産を重視する国際的な動きや国内の雇用関連制度改善の動きを受け、企業に人的資本経営の推進や人的資本に関する情報開示を求める動きが活発化しています。非常に良い傾向だと思われる一方で、懸念される事象も起きています。 本稿では、人的資本経営を組織の未来をデザインするための力とするべく、求められる姿勢や視点を紹介します。

Talent Management Review vol.2
タレントマネジメントとは、「会社として人材管理機能全体(採用〜代謝)のレベルを事業に同期させて、向上させる取り組み」と整理できます。 この考えのもと、多くの企業でタレントマネジメントシステムの導入が進む一方、十分に活用しきれていない企業が多いのが現状です。 本書では、タレントマネジメントシステムの活用がうまくいかなくなる理由とその解決策を紹介します。

SAP BTPがなぜ必要か?S/4HANA導入時の課題とBTPでの解決の方向性

~NTTデータグループのノウハウで実現する組織人事革新~

SAP NOW AI Tour Tokyo & JSUG Conference

第14回 人材マネジメント研究会

事業価値を高めるデータ活用施策実現に必要な考え方とは

パブリッククラウド型基幹システム導入成功に導く4つの事前検討

人事システム導入プロジェクトはDX人材育成の好機

ジョブ型を取り入れる前に考えておきたいこと

後期・単身高齢者の増加に対応する新たな社会システムの構築に向けて

“運用”に潜む落とし穴を回避し、制度を成功させるための対応とは

業務標準化に向けた基幹システム刷新手順

【第2回】人事業務をエコシステム化した際の落とし穴を回避するには

【第1回】人事業務の変遷とエコシステムという選択肢

クラウド業務改革EXPO

「接続性」「透明性」「柔軟性」から見るコミュニケーション変革設計とは

米国証券取引委員会のルール改訂は他人事か

人事PMIの全体像と基幹人事制度統合の進め方

【第3回】女性活躍推進を成功させる“意識改革・チェンジマネジメント”

【第2回】ワーキングママ・パパの活躍を支える施策

急速に変化する環境に対し、俊敏に適応するアジャイル組織のケイパビリティ

高卒採用のトレンド変化と採用活動の変革

新卒採用者離職防止に必要な真のエンゲージメント向上施策

Z世代にアプローチする採用チャネル活用術

FTEからの脱却、要員計画で必要な視点
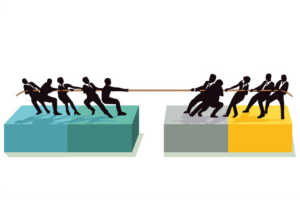
人的資本の情報活用が紡ぎだす経営の“未来”

未来につながる人的資本開示の“仕組みづくり”

ソフトウェア&アプリ開発展

プロジェクトを成功させるために知っておきたいプロジェクト推進側と導入ベンダー側の「意識の差」
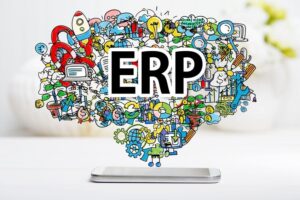
人的資本の情報整備と、開示への1stステップ

【第1回】女性活躍推進の基本的なステップ

そのKPIは信頼できるか?人材データの健全性とその効用

“やらされ”開示対応にせず実業務に生かすためのKPI設定

Talent Management Review vol.2

メタバース導入がタレントマネジメントに与える影響

メタバース導入がビジネス活動と社員向けサービスに与える影響

倉庫業務をEnd to Endで可視化するアプローチと実現に向けたポイント

人的資本の情報開示およびISO30414の概要を理解する

SAP標準機能を最大限に活用し短期間・低リスク・低コストを達成するために

ダイバーシティ推進の課題と人事の役割

ERP導入を検討する際に、はじめに実施すべきブループリントフェーズ
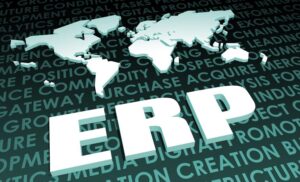
情報間の構造を明らかにし、情報の価値を高める
