データマネタイゼーション調査レポート
データマネタイゼーション事業立ち上げ経験者300名を対象に実施した定量調査に加え、20社以上へのインタビューとコンサルティング現場での経験を踏まえ、データマネタイゼーション事業の成功に向けたポイントを解説します。


POINT 1
医療機関では、医師、看護師、薬剤師、放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、栄養士、事務職員など、多職種が連携して日々の医療提供を担っている。これら多職種の業務を支えるのが病院情報システムであり、診療録(カルテ)の役割を担う電子カルテシステムを中心に、各職種に特化した部門システムと密に連携して構成されている。医療機関の機能によってシステムの構成は異なるものの、一般的に50種を超えるシステム群により病院情報システムは形成されている。通常、オンプレミス構成の場合には、ハードウェアやソフトウェアの保守期限到来に伴い5〜7年のサイクルで更新が必要となり、都度、現状分析から導入・稼働後評価に至るまでのプロジェクトが実施される。
日本の医療制度では傷病名や治療法に対して公定価格といえる診療報酬が設定されており、国民はどの医療機関であっても全国一律の価格で医療を受けることができる一方、医療機関側の収入も一律となる。これにより、医療機関は常に限られた資源の中で質の高い医療を提供する工夫が求められ続ける。そのような中、病院情報システム更新の大きな壁となるのが、システム更新費用の高騰である。昨今のあらゆるコスト上昇の影響もあり、既存システムと同等の機能・性能を維持するだけでも前回比2倍近くに膨れ上がった概算見積を手にするケースもある。こうした状況下で、いかにコストを抑えつつ、費用対効果の高い病院情報システム更新を実現するかが大きな課題となっている。
コスト抑制を重要視する経営層、操作性や更新作業の負担軽減を重視する現場職員、それぞれの視点を多角的に把握し、複数のアプローチから解決策を導出した。
POINT 2
公平な製品検討と仕様策定
病院情報システム更新における要件定義は、次期システムを用いた業務改善を検討する機会でもあり、業務フローの見直しや部門間連携の強化も期待される。
また、従来は障壁とされていた「電子保存の三原則」を担保したデータ移行の低コスト化も進み、特定ベンダに依存しない製品選定が可能となってきたことから、現行の機能や運用フローに囚われることなく、客観的な姿勢で複数ベンダ製品の比較検討を実施した。ベンダの協力も得て展示会形式でのデモンストレーションを実施し、多くの職員が最新機能を実際に確認・評価し、有用だと意見された機能を反映した仕様策定を実施した。また、その過程において詳細要件の実現可否について時間をかけて各社に確認することで公平性を担保した。これにより、ベンダ間の健全な競争を促すとともに、よりよい製品をよりよい価格で採用したいという医療機関側の意向に沿った調達を実現した。
医療DX・働き方改革への順応
医療機関が個々に保有している医療情報の施設間共有の必要性はかねてから明らかであり、地域単位での情報共有を実現する地域医療連携ネットワークの整備が個別に進められてきた。一方、コロナ禍をきっかけに全国横断的な医療情報共有の重要性が高まったことで、医療DXの各施策(オンライン資格確認等システム、電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスなど)が国の施策として飛躍的に進展している。また、時期を同じくして医療職の働き方改革の意識も高まり、業務効率化やタスクシフトが求められるようになった。
そこで本プロジェクトでは、病院情報システム、地域医療連携ネットワーク、医療DXのそれぞれの役割を明確に整理することで、機能の重複や二重入力といった無駄を排除し、病院情報システムに蓄積された医療情報の利活用を前提としたシステム要件を再構築した。これにより、コスト最適化と業務効率の向上を両立した。
ノンカスタマイズ志向の電子カルテシステム導入
電子カルテシステムを含む病院情報システムは従来、医療機関個々の運用フローにシステム機能や使い勝手を適合させる「カスタマイズ型」のシステム構築が主流であった。近年、ベンダによる導入実績の蓄積とパッケージ機能の成熟により、運用をシステムに合わせる「ノンカスタマイズ型」での導入も可能となってきた。特に高度急性期医療機関においては多数のカスタマイズが行われるのが一般的であったが、コストの高止まりやベンダーロックイン、法制度改定時の特別対応コストの発生などが課題であった。そこで、本プロジェクトではカスタマイズ機能の全面的な棚卸による不要機能の洗い出しと最適化を実施した。結果として、実装されたものの使用されていない機能や代替可能な機能が多数あることが明確となり、機能の最適化によるコスト削減と効率化を実現した。
POINT 3
1.医療現場を理解したプロジェクト推進
病院情報システム更新検討においては既存の課題を棚卸し、可能な限りの解決を図っていく。課題収集はアンケートを用いるだけでなく、ヒアリングにより職員の本音や課題の本質を分析して解決に向けた議論を行った。現場が抱える課題は職種や部門により千差万別であり、各専門職が担う業務内容や現場での運用を十分に理解した上で解決策を検討する必要がある。弊社ヘルスケアチームは上級医療情報技師や診療情報管理士といった医療情報に係る資格保有者や、医師、看護師、臨床検査技師、理学療法士といった臨床経験を有する者で構成されており、医療現場が納得する解決策を都度、提案できたことがプロジェクト成功要因の一つである。
2.中立性と豊富な経験
病院情報システムは多くのベンダにより提供されており、医療機関が採用している製品も多岐に亘っている。そんな中、弊社は特定のシステムベンダに依存せずに中立的立場を徹底している。その結果、各ベンダの製品の違いや導入・保守体制の違いをノウハウとして積み重ねてきており、各医療機関の抱える課題に即したコンサルティングの実行が可能となっている。中立的で公平な検討を推進する姿勢はシステムベンダからも評価されており、結果としてベンダ間の競争性を高めることにも繋がっている。また、弊社はこれまでに数多くのベンダ変更事例を有しており、いずれの医療機関でも大きな混乱なく新システムへの移行を実現している。今後も、豊富な実績と医療現場に根差した視点を活かし、病院情報システムの最適化を支援していく。
データマネタイゼーション事業立ち上げ経験者300名を対象に実施した定量調査に加え、20社以上へのインタビューとコンサルティング現場での経験を踏まえ、データマネタイゼーション事業の成功に向けたポイントを解説します。

~企業内の最後の暗黒大陸、調達購買業務の見える化を進める~
企業のDXが進むなか、調達購買業務のDX、なかでも購買取引に関するデータの収集・分析・活用は、ほとんどの企業ができていません。 なぜ調達購買業務のDXは進まないのでしょうか? 多くの企業の調達購買業務DXに関する現状と、共通する課題を掘り下げ、今後の調達購買業務DXの進め方について解説します。

事業化に向けたメタバースビジネスの検討に携わったことのある経験者500名への調査と、20名へのインタビューをもとに「事業化に失敗するメタバース13の特徴」を導出、事業化成功に向けたノウハウを解説します。

なぜ91%のサブスクは失敗するのか?
サブスク事業経験者500名への定量調査から判明した、「失敗するサブスク 17の特徴」について解説します。 コンサルティング現場での経験を踏まえ、サブスク事業の成功・失敗に関わるノウハウを「フォーティエンスの提言」として提示。

第45回医療情報学連合大会(第26回日本医療情報学会学術大会)

![【連載寄稿】[キャリア解説]理学療法士、コンサルティングファームへ - 命と向き合い手にした、プロフェッショナルマインドを武器に](https://www.fortience.com/wp-content/uploads/2025/11/170167387_s-300x163.jpg)

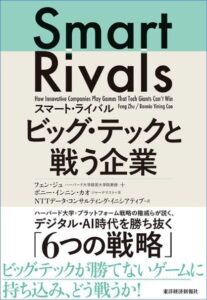
ローコード×AIで変わる要件定義──エンジニアと業務の新しい関係

すぐに役立つPDFの読み込みから、データモデルの初歩まで

第44回医療情報学連合大会・第25回日本医療情報学会学術大会
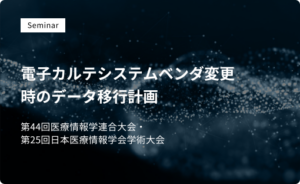
Python in ExcelとPower Queryで実現する効率的なデータ処理

データ統合に不可欠なIT部門の推進力

押さえるべきAIマネジメントフレームワークと小売企業におけるAIマネジメント導入事例

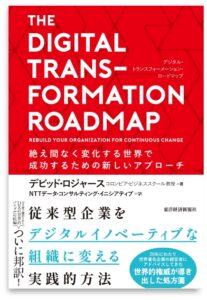
検討時に立ちはだかる「デバイス」「コスト」「ROI」の壁を乗り越えるために

Power Queryを活用した基本事項点検のススメ

成果を生むAIを導入するためには(特別編)
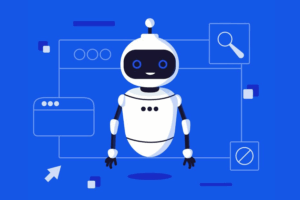
企業におけるChatGPT活用の最新ユースケース

ChatGPTの社会的インパクトと可能性

人工知能/大規模言語モデルの発展と社会への影響

デザインアプローチで導出する「DXに取り組むべき理由」

サステナブル企業が取り組んでいるSDGsテックの考察

DXを加速するデータドリブンカスタマージャーニー

Withコロナ/AfterコロナのDX・デジタル技術活用とは

成果を生むAIを導入するためには(後編)
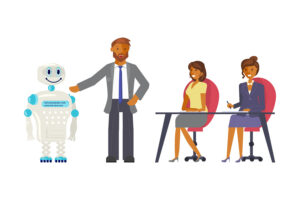
成果を生むAIを導入するためには(前編)
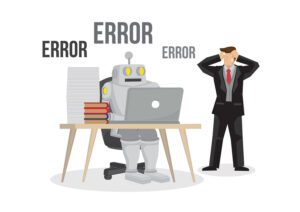
変革に必要な真のデジタル技術活用とは
